「小児科看護師になりたいけど、自分に向いてるのかわからない……」と悩んでいませんか?
小児科で働く看護師には「子どもが好き」という気持ちだけでなく、子どもや保護者を支える能力が必要です。
とはいえ、その実態はなかなか想像できないもの。
この記事では、小児科看護師に向いてる人の特徴や仕事内容、やりがい、つらいことをくわしく解説します。
小児看護に興味がある方は、自分に適性があるかを確認し、キャリアの参考にしてみてください。
小児科の看護師に向いてる人の特徴5つ
小児科の看護師に向いてる人は、以下の特徴があります。
- 子どもが好き
- すぐれた観察力がある
- 体力に自信がある
- 精神的なタフさがある
- コミュニケーション能力が高い
くわしく解説します。
子どもが好き
子どもと接するときに自然と笑顔になれる人は、小児科の看護師として活躍しやすいでしょう。
たとえば、乳児にはスキンシップや声かけで安心感を与え、幼児には遊びを交えながら接することで信頼関係を築けます。
処置や手術などに対して恐怖心を持つ子どもを安心させるために、個人の性格や発達段階を理解した優しい態度が求められます。
すぐれた観察力がある
子どもは自分の症状をうまく伝えられないことが多いため、顔色やしぐさ、泣き方などから病状を判断する観察力が必要です。
とくに乳幼児は、呼吸音や皮膚の色、食欲の変化など、わずかなサインから体調不良を読み取る力が求められます。
こうした小さな変化に気づく力が、適切な小児看護につながります。
体力に自信がある
小児科では、抱っこや移動のサポートなど体を使う場面が多く、体力が必要です。
夜勤中に夜泣き対応に追われることもあり、小児科ならではの大変さがあります。
また、小児科では「子どもをあやしながら処置をする」「素早く動いて安全を確保する」といった場面も多く、瞬時に対応できる柔軟性や持久力も求められます。
精神的なタフさがある
小児科看護師は、精神的な負担に耐え、冷静に対応できる強い精神力を持つ人に向いています。
小児科では体調を崩した子どもたちと向き合い、治療の痛みやつらさに寄り添う場面や、ときには別れの悲しみを経験することもあります。
それでも、子どもやご家族の前では気丈に振る舞わなければなりません。
なかには「子どもの苦しむ姿を見るのがつらい」といった理由で、小児科を離れる看護師もいます。
そのため、小児科の看護師にはつらい経験を乗り越えられる精神が必要です。
コミュニケーション能力が高い
子どもが自然に気持ちを表現できるようなコミュニケーションをとれる人は、小児科で能力を発揮できます。
子どもと信頼関係を築くには、日常のかかわりから出てくる何気ない一言や表情から本音を読み取り、適切に対応する能力が求められます。
子どもにとっては「白衣=怖い」と感じることもあるため、優しい表情や落ち着いた声のトーンなど、安心感を与える工夫が必要です。
また、小児科では保護者とも密接にかかわります。
親の不安をやわらげ、適切な説明をするために、コミュニケーション能力が重要です。
小児科看護師の役割
小児科に勤務する看護師の役割は、以下のとおりです。
- 子どもの心身のケア
- 保護者へのメンタルケア
- 子どもの成長・発達のサポート
小児科看護師ならではの特徴を見ていきましょう。
子どもの心身のケア
病気やけがの治療だけでなく、不安や恐怖心とたたかう子どもの心のケアが小児科看護師の重要な役割です。
入院や治療に対するストレスを軽減し、安心して過ごせる環境をつくることが求められます。
ときには、言葉ではなく寄り添うことで安心感を与える「非言語的コミュニケーション」が必要になることもあります。
子ども一人ひとりの性格や発達段階に応じた対応をおこない、信頼関係を築くことも大切です。
保護者へのメンタルケア
子どもが病気になると、保護者も不安を抱える傾向にあるため、看護師は病状や治療方針をわかりやすく説明し、精神的なサポートをおこないます。
また、保護者の方のなかには「自分の話を聞いてもらいたい」と感じている方も。
不安な状況が続くと、抑うつ状態になってしまうことも少なくありません。
そのため、看護師は単に医療的な情報を伝えるだけでなく「いつでもお話をうかがいますよ」という姿勢を見せることが大切です。
子どもの成長・発達のサポート
小児科の患者さまは発達途中の子どもが多く、身体的・精神的な成長を見守りながら適切なケアを提供することが大切です。
これまで病院への入退院をくり返していたり、自宅療養が長かったりする場合、発達課題を順調に歩めていない子どもも少なくありません。
そのため、個々の発達における課題や病気による症状に合わせてかかわることが、小児科看護師には求められます。
また、子どもが安心して社会に適応できるよう、医師やリハビリスタッフと連携しながらサポートすることも、小児科看護師の役割のひとつです。
小児科看護師の仕事内容
小児科看護師の仕事内容は、以下のとおりです。
- 診察の補助
- 処置や治療の実施
- 子どもとの遊びを通じたケア
- 保護者への説明と支援
成人の看護と共通する部分もありますが、小児科ならではの工夫が必要な場面もあります。
くわしく見ていきましょう。
診察の補助
医師の診察をスムーズに進めるために、子どもが安心できるようサポートします。
「これからこうするよ」「そばにいるから大丈夫だよ」と優しく声をかけ、不安をやわらげることが大切です。
診察後には「よく頑張ったね!」とたくさんほめることで、次回の診察への抵抗感を減らすことにもつながります。
処置や治療の実施
一般病棟の看護師と同様に、小児科でも点滴や注射、処置などをおこないます。
点滴や処置をする前には、かならず年齢や発達段階に応じた説明が必要です。
検査や治療の必要性を説明することを「プレパレーション」とよび、子どもの場合においても、必要な技術です。
たとえば、安心させるために「痛くないよ」と言った処置が実際に痛みともなった場合、年齢や発達段階によっては「だまされた」と感じるかもしれません。
すると、医療従事者や処置などに不信感を抱き、今後の治療がスムーズに進まなくなるおそれがあります。
そのため、かならず納得してもらったうえで、ケアや処置をおこなうことが大切です。
子どもとの遊びを通じたケア
病気の子どもが少しでもリラックスできるように、遊びを取り入れながらケアをおこないます。
たとえば、おままごとやお絵描きを通じて、子どもが抱えている不安や願いを自然に表現することがあるため、看護師はささいな一言に敏感にならなければなりません。
遊びを単なる娯楽ではなく、子どもの心のケアやコミュニケーションの手段の1つと考え、安心して過ごせる時間をつくることが大切です。
保護者への説明と支援
医師が説明した病状や治療方針を、わかりやすくなるよう噛み砕いて補足し、親の不安をやわらげるよう努めます。
なかには、心配するあまり攻撃的な行動をとってしまう保護者の方もいます。
そうした方にも冷静に対応し、気持ちを落ち着かせてあげられる声がけをおこなうのも、大切なケアです。
子どもは保護者の感情に敏感です。
そのため、保護者の安心が子どもにもよい影響を与えることが期待できます。
小児科の看護師に必要な資格
「小児科の看護師は資格が必要なのでは」と思われがちですが、小児科で働くだけなら特別な資格は必要ありません。
くわしく解説します。
小児科で働くなら看護師免許のみでOK
小児科病棟で看護師として働きたい場合は、看護師資格さえあれば可能です。
異動となると数年の実務経験が重視される傾向ですが、新人であっても配属されるため、特別なスキルも必要ありません。
小児看護を深く知りたい、小児科病棟で役立つ資格がほしいなどの方は、つぎで紹介する資格の取得を目指すとよいでしょう。
小児看護に活かせる資格
小児科に役立つ資格として、以下があげられます。
| 小児看護で役立つ資格 | 役立つ理由 |
|---|---|
| 保育士 | 発達段階に応じたかかわり、保護者支援、子どもの心理的ケアに役立つ |
| 臨床心理士 | 子どもの心のケアや保護者の精神的サポートに役立つ |
| チャイルドマインダー | 少人数保育の知識が身につき、個別対応のスキルが向上する |
これらの資格を取得することで、看護師以外の視点で子どもとかかわれるようになるでしょう。
ただし、資格によって条件が設けられている点に注意してください。
小児分野に特化した資格
小児に特化した看護師としてスキルアップしたいなら、以下の資格取得を目指しましょう。
- 小児看護専門看護師
- 小児プライマリケア認定看護師
- 新生児集中ケア認定看護師
これらの資格を取得することで、小児医療に関する専門的な知識や技術を深め、より質の高いケアを提供できるようになります。
自分の目指すキャリアに合わせて資格を選び、スキルアップを目指しましょう。
小児科看護師のやりがい
小児科で働く看護師のやりがいは、以下のとおりです。
- 専門性を高められる
- 子どもの成長や回復を見守れる
やりがいを知れると、小児科で働く魅力を感じられます。
専門性を高められる
小児科では、子ども特有の病気や発達段階に応じたケアが求められるため、専門的な知識や技術を習得できます。
成人看護とは異なる視点で経験を積めるため、スキルアップにつながる環境と言えるでしょう。
子どもの成長や回復を見守れる
子どもの成長や回復を間近で見守れることも、小児科看護師として働く魅力の1つです。
治療を受けながら少しずつできることが増えたり、不安そうだった子どもが落ち着いて処置を受けられるようになったりと、日々の小さな変化に喜びを感じられます。
また、病気やけがでつらい思いをしていた子どもが回復し、笑顔を見せてくれる瞬間は大きなやりがいにつながるでしょう。
小児科看護師のつらいこと
小児科で働く看護師はやりがいがある一方で、精神的・技術的に難しい場面も多くあります。
くわしく解説します。
病状の読み取りが難しい
子どもは自分の症状を言葉で説明できないことが多く、わずかな表情やしぐさ、泣き方の違いなどから病状を判断する力が必要です。
的確な対応をするためには、自身の観察力を磨きつつ、医師やほかの医療スタッフと連携を取りながら情報を共有することが大切です。
子どもの病気や死と向き合う場面がある
小児看護では、ときに命にかかわる状況に直面します。
悲しい別れを経験することもあり、そのたびに強い心を持ち続けなければならず「つらい」と感じる看護師も少なくありません。
仕事を続けるうえで、精神的なケアやストレスマネジメントを意識することが大切です。
保護者からのプレッシャーが大きい
小児科では、保護者の不安や期待が強く、厳しく要求されることも珍しくありません。
子どもの症状が思うように改善しない場合、保護者の不満が看護師に向かうこともあるでしょう。
こうした保護者のプレッシャーの大きさが、精神的な負担となる場合があります。
ただし、不安や期待の裏には保護者の自責の念や不安があることがほとんどです。
こうした保護者の気持ちも理解しつつ、看護師自身も精神的な負担を抱えすぎないよう、チームで支え合いながら業務をおこなえる環境が必要です。
小児科で働く看護師の1日の流れ【病院の場合】
病院の小児科で働く看護師の1日の流れは、以下のとおりです。
| 時間 | 業務 |
|---|---|
| 出勤前 | ・情報収集 ・必要な検査やケアをメモ |
| 8:00~9:00 | ・申し送り(全体、個別) ・ラウンド |
| 9:00~12:00 | ・ラウンド ・食事介助(ミルク、離乳食) ・処置、検査 ・おむつ交換 ・プレイルームでの遊び |
| 11:00~13:00 | ・昼休憩 |
| 13:00~16:30 | ・ラウンド ・おむつ交換 ・ご家族との面会対応 |
| 16:30~17:00 | ・記録 ・申し送り |
あくまでも目安であり、施設によって異なります。
子どもの状態をこまめに観察しながら、食事や投薬、清潔ケアなどさまざまな業務を担います。
小児科の看護師が働く場所
小児科の看護師が働く場所は、おもに以下のとおりです。
- 総合病院
- 小児専門病院
- 小児集中治療室(PICU)
- 新生児集中治療室(NICU)
- 訪問看護
- 小児科クリニック
- 重症心身障害児施設
- 保育園・幼稚園
- 学校(保健室)
たとえば、総合病院や専門病院では小児に特化した医療技術を学べ、訪問看護や小児科クリニックでは自宅での過ごし方に密着できます。
同じ小児科でも、子どもが過ごす環境によって看護師の役割は変化します。
自分がどの分野で子どもとかかわりたいかを検討して、転職を視野に入れるとよいでしょう。
小児科の看護師の年収事情
小児科だからといって、特別な手当はありません。
診療科ごとの年収について明らかなデータはありませんが、一般的な看護師と同様に508万1,700円が平均であると推測できます。
ただし、看護師以外の資格を取得している場合は、相応の資格手当が支給されることもあります。
小児科看護師に向いてる人は子どもが好きなだけではない。専門性を高めて子どもと家族を支えよう!
小児科看護師に向いてるのは、単に子どもが好きなだけでなく、専門的な知識やスキルを身につけ、子どもや保護者を支えられる人です。
子どものわずかな変化を見逃さない観察力や、適切な判断力が求められるほか、不安を抱える保護者と信頼関係を築くコミュニケーション能力も欠かせません。
命と向き合う場面や精神的な負担もありますが、子どもの回復を見守れるのは小児科ならではのメリットです。
小児科看護師を目指す方は、これらの資質を意識しながら、専門性を高めて成長していきましょう。
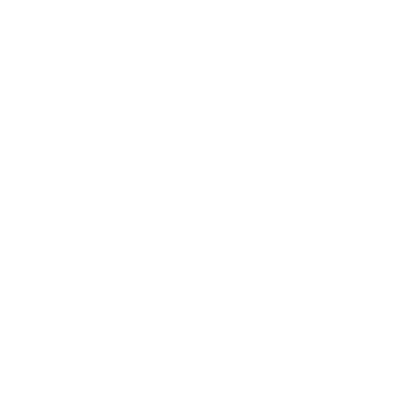 Join Nurse!
Join Nurse! 


